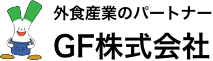【DX戦略】
社会・競争環境の変化に対する認識とDX推進の必要性
現代はVUCAの時代にあり、グローバルではパンデミック、地政学的リスク、気候変動など、日本国内では少子高齢化やダイバーシティ化など、予測困難な課題が次々と発生しています。
こうした環境変化に対し、デジタル技術の進化は企業にとって大きな機会であると同時に、対応を誤ればリスクともなり得ます。
当社は、これらの変化に柔軟かつ迅速に対応するため、DXの推進を重要な経営戦略と位置づけています。
特に、物理的データ(IoT・センサー・RPA等)と属人的データの双方を活用することで、業務の高度化、生産性向上、技術伝承、多様性への対応を図り、持続的な競争力の確保を目指しています。
経営ビジョンとDXの位置づけ
当社は「青果拡張業(VEH)による、持続可能で環境にやさしいウェルネス社会の実現」を経営ビジョンとして掲げています。
このビジョンの達成には、DXの活用が不可欠です。青果のアップサイクルによる資源活用、IoTやAIによる作業品質の向上、属人的な技術の多言語・横展開による標準化、そしてFSSC22000などの国際認証取得を通じたグローバル展開まで、すべての取り組みにおいてDXを中心に据えています。
DXを通じて、当社は「環境配慮」「働きがい」「健康の提供」を三本柱とした新たな価値創出に取り組んでいます。
DXを基盤とした持続可能なビジネスモデルの構築に向けて
当社GF株式会社は、DXを基盤とした戦略を通じて、生産ラインの自動化、ロボティクスの導入、ウェアラブル音声識別システムによる現場管理、RPAによる業務効率化、社内データベースの整備などを積極的に推進しています。これらの施策により、VEH(青果拡張業)の実現に向けた持続可能なビジネスモデルの構築を進めております。
私たちは、これらの取り組みを通じて、全てのステークホルダーの皆様に対し、より大きな価値を提供し続けることを使命としています。今後も、ビジネスモデルの進捗状況や成果
について、経営の立場から継続的に情報発信を行い、社内外との透明性あるコミュニケーションを図ってまいります。
更なる業務効率化と価値提供の継続により、すべてのステークホルダーの満足度向上と、持続可能な社会の実現に向け、誠心誠意取り組んでまいります。
GF株式会社 代表取締役 王 志敏
DX戦略の概要(経営ビジョン・ビジネスモデル実現のための方策)
経営ビジョンの実現に向け、当社は以下の3つの軸を中心にDX戦略を推進しています。すでに各施策は段階的に導入・稼働しており、現在はその運用定着とさらなる高度化を図るフェーズへと進化しています。
・社内業務のデジタル化と自社データベースの構築
業務を「物理的データ(IoT・RPAで取得)」と「属人的データ(ウェアラブルAIで取得)」に分類し、それぞれをデジタル化。特にIoTによる調理温度管理はすでに稼働し、品質と作業精度の向上に貢献しています。また、機械管理・勤怠管理システムの導入も完了し、販売管理もオンプレミスからクラウドへ移行。これらのデータを活用する 自社データベースの構築が始動しています。今後はこれらを統合・連携させ、さらなる生産性の向上と技術の横展開、ヒューマンエラーの削減を目指します。
・従業員のリスキリングと組織的なDX推進体制の構築
社内では「GF大学」グループチャットを用いた情報共有・教育を継続的に実施し、業界の最新知見や品質管理、DXに関する知識の向上を図っています。定期的なDX勉強会も 開催しており、従業員のデジタルリテラシー向上と実践力の底上げに繋がっています。今後は、習得スキルの可視化や個別育成プランの充実も検討しています。
・多言語化・ペーパーレス化・自動化によるグローバル展開と業務効率化
DropboxやLINE、WeChatを活用し、工場への生産指示などの社内外連絡をすでにペーパーレス化。さらに、RPAも導入し、一部の請求書発行やメール配信業務の自動化が 稼働しています。今後はRPAの活用範囲を拡大し、さらなる業務効率化とグローバル対応強化を進めていきます。
データ活用の方策(DX戦略の詳細)
当社のDX戦略におけるデータ活用は、以下の具体的施策に基づき、導入と運用を進めています。
1.生産現場におけるIoT・センサーによる物理的データの収集と利活用
すでに調理温度のIoT管理は稼働を開始しており、品質の安定化と作業の見える化に効果を発揮しています。今後は湿度・電力使用量・原材料比率など他のデータとも連携
させ、異常検知や予防保全の精度向上、さらなる省エネ運用にも取り組みます。
2.属人的データのAI音声識別による収集と多言語化・記録化
作業中の会話やノウハウをAIで音声認識・翻訳し、記録・教育コンテンツへと転用する仕組みを構築中です。今後は外国人労働者対応やマニュアル自動生成機能の強化を 通じて、技術伝承の多言語対応と属人性の排除を進めます。
3.バックオフィスにおけるデータの蓄積と業務の自動化
勤怠・売上・衛生・在庫などのデータが各システムで稼働しており、RPAによる請求やメール処理の自動化も開始。今後はこれらの連携による統合運用や、EPA・CAなどの海外展開先での活用も視野に入れています。
4.データベースの構築と利活用(DXの中核)
販売管理・勤怠・機械・衛生などのデータベース構築が進行中で、将来的には統合ダッシュボードによりリアルタイムで業績や現場状況を把握可能にします。さらに、AIを 活用した予測分析・改善提案・マーケティング高度化への展開を計画しています。
当社のDX戦略は、単なるIT導入に留まらず、業務プロセスそのものの質的変革(“X”の実現)を目指しています。今後も現場とデータを繋ぎ、組織全体が進化し続ける仕組みを
整えつつ、得られた知見や成果を業界全体に還元することで、日本の食品産業の持続的な発展に寄与してまいります。
DX戦略を効果的に進めるための体制
当社では、DX戦略の円滑な推進と全社的な浸透を図るため、新規事業本部長を筆頭とする「DX推進チーム」を設置しています。本チームには、総務部長および各工場長がメンバーとして参画し、経営陣と連携しながら部門横断的に戦略を実行する体制を整えています。
この体制のもと、業務のデジタル化、データ基盤の構築、業務自動化といった各種DX施策を段階的に進めており、現場の実情に即した改善と効率化を実現しています。
さらに、DXを実現するためには人材の育成と確保が不可欠であるとの認識のもと、社内教育制度「GF大学」やグループチャットを活用した知識共有、定期的なDX勉強会の開催を通じて、全従業員のリスキリング(再教育)を推進しています。これにより、デジタルリテラシーや業界知識を体系的に学ぶ機会を提供し、DX人材の底上げと定着を図っています。また、DX推進にあたっては外部組織との連携・協業も積極的に行っており、システム導入を外部パートナーの協力のもとで進めています。
これらの外部協力により、現場に即したデータの収集と利活用が可能となり、業務の最適化、品質向上、ペーパーレス化といった成果につながっています。
今後も、組織体制の整備、人材の育成、外部との協業という3つの柱を軸に、DX戦略を着実に推進し、経営ビジョンおよび新たなビジネスモデルの実現を目指してまいります。
情報処理技術を活用するための環境整備
当社では、定期的な経営会議にてDXの進捗確認と予算決定を行い、攻めのIT投資に向けた重点的な予算配分を継続しています。これまでに、ウェアラブルAI音声識別システムの導入や、紙帳票・Excel管理といったレガシーシステムから、統合データベースおよびRPAを活用した最新の業務システムへの刷新を段階的に進めてまいりました。
現在は、これらのシステム基盤をさらに活用・発展させる段階に入り、AIによる議事録作成や自動翻訳技術を活用したコミュニケーションの効率化など、業務のさらなる最適化を目指しています。また、DX推進人材の育成と最適な配置を引き続き強化し、全社的な変革と価値創出に向けて、取り組みを一層加速させてまいります。
DX戦略達成指標の決定
当社では、DX戦略に基づく取組状況を定期的に把握・評価し、次のアクションに活かすため、以下の定量・定性指標を設定し、定期的に評価を実施しています。これにより、PDCAサイクルを継続的に回し、戦略の実効性を担保しています。
・事務従業員の残業時間:平均残業時間ゼロを目標とし、勤怠データにより評価
・ヒューマンエラー件数:製造現場における人的ミス(転記ミス、指示誤り、消費期限設定ミスなど)の月次件数をトラッキングし、ゼロ件を目指す
・従業員のストレス指標(定性):匿名アンケートによる定期的なストレス評価(5段階評価)でストレスの軽減を確認
・ 社内経費削減率:ペーパーレス化・RPA導入による運用コスト削減率を毎年算出し、3%以上の削減を目指す(財務指標と連携)
・RPA導入率:全バックオフィス業務に対するRPA化の進捗率(導入済タスク/対象タスク)を定量的に記録
・データベース構築の進捗状況:販売管理・勤怠管理・衛生管理等の各分野におけるデータベース構築完了率を指標化
・従業員のDX教育参加率:社内教育(GF大学・DX勉強会)の参加者数を定期集計し、教育浸透度を確認